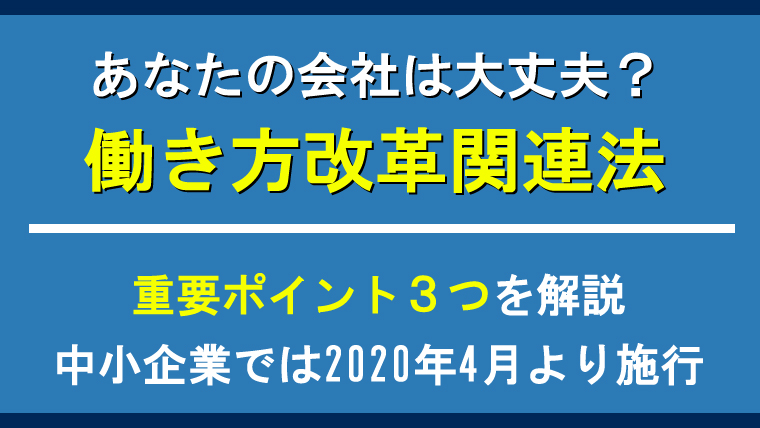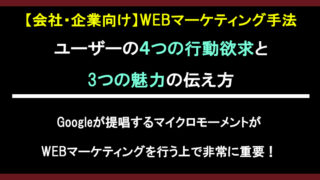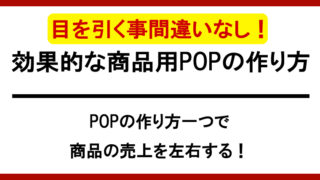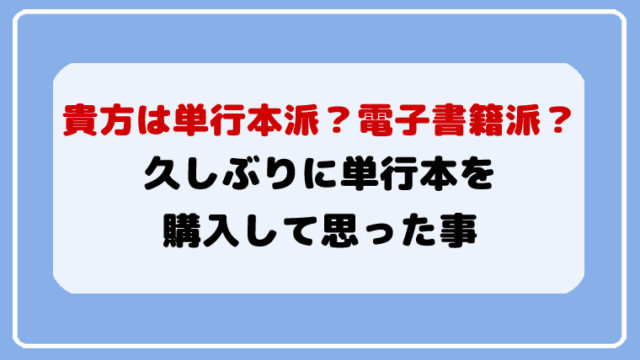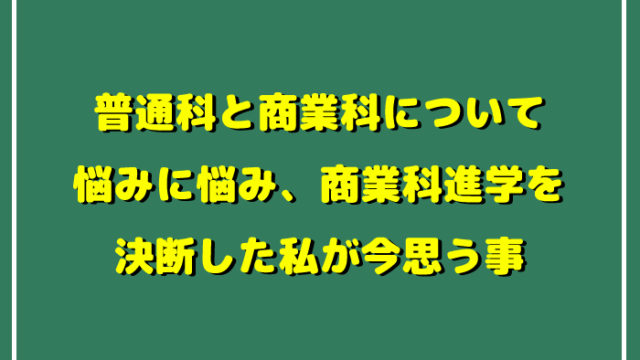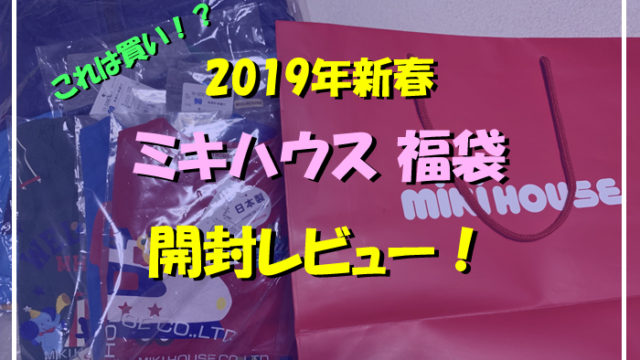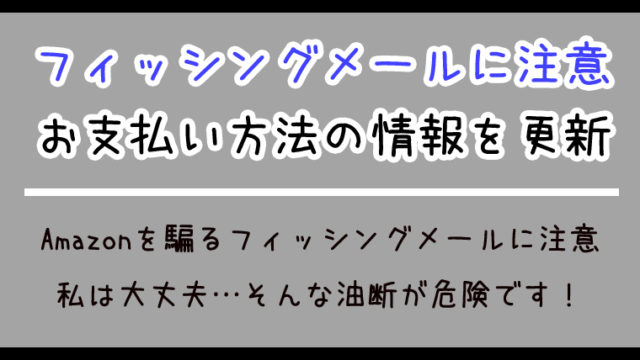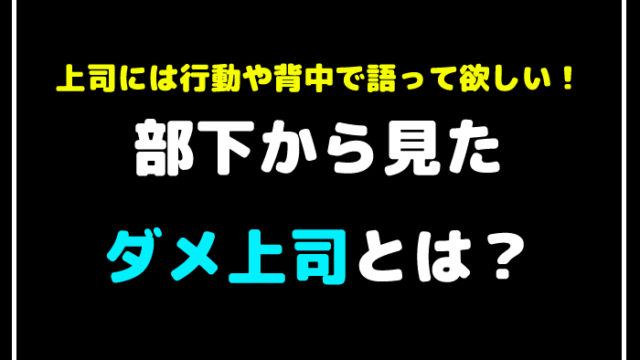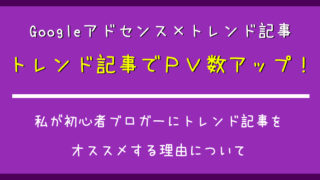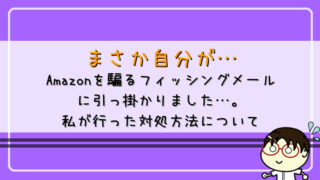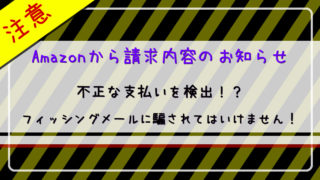大企業では既に施行されている「働き方改革関連法」ですが、中小企業では2020年の4月より施行されます。
この働き方改革関連法は政府が掲げている“ニッポン1億総活躍プラン”の実現の為に働き方を変えていかないといけないという事で施行が始まりました。
誤解されやすいんですが、この働き方改革関連法の正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」で、この法自体が直接的な力を持つというものでは無く、既に施行されている労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法といった労働法の改正を目的とした法律なんですね。
今回は働き方改革関連法の中でも私が特に重要だと思う3つのポイントを紹介させていただきます。
働き方改革関連法:①長時間労働の規制
そもそも労働時間は労働基準法(以下、労基法)という法律でしっかりと明記がされています。
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
引用:労働基準法第32条より
簡単に説明すると会社は社員に対して1日8時間以上、1週間に40時間以上働かせてはいけないという法律で、これを法定労働時間と言います。またお昼休憩等の休憩時間は含みません。
おかしいですよね?恐らく皆さんもっと長時間働いているはずです。
そこで登場するのが36協定(さぶろくきょうてい)なんですね。恐らく1度は聞いた事があると思います。
36協定で時間外労働を可能に
残業時間を36時間以内に抑える為のものだ!と勘違いされる方も多いようですが、この「36」とは労基法”第36条”からきています。
では労基法第36条がどのようなものなのか。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
引用:労働基準法第36条より
簡単に説明すると、
- 労働組合がある会社は労働組合と
- 労働組合がない会社は労働者の過半数代表者と
書面をもって協定し、労働基準監督署に届け出る事で残業させて働かせる事も、休日に出勤させる事も出来るという事です。
労働者の過半数代表は管理職といった経営側の人間ではダメです。また、選考の際も「投票」や「挙手」といった明確な民主的手続きが必要です。
仮に管理職といった経営側の労働者を勝手に過半数代表に選出して36協定を締結してもその協定は無効になりますからね!
そしてこの36協定には今まで法律上の「上限」が無かったんですね。
36協定を締結すると一般的には月45時間、年間で360時間(行政指導)まで労働者に残業させる事ができ、この上限時間も「特別条項」を締結する事で年に6回までという制限はありますが、月の残業時間自体は45時間を超えても残業させる事が可能でした。
そこで今回の働き方関連法でこの部分に法律上の「上限」を設定する事が決定した訳です。
【36協定】法律上の上限
- 月に45時間、年間360時間(原則)
- 複数月平均80時間、月100時間未満、年間720時間(特別条項)
上記のように法律上の上限が出来たという事です。これによって月に100時間以上残業させてしまったらその時点で違法行為になる訳です。
より詳しく知りたい方は厚生労働省のホームページからも確認する事ができます。
働き方改革関連法:②公正な待遇確保
よく同一労働同一賃金と言われているもので、同じ仕事をしているのであれば、雇用形態に関係なく同一の賃金を支払うべきという事。
現在の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート有期法)の第8条で不合理な待遇が禁止されています。
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
引用:パート有期法第8条
上記は改正後の法律で、簡単に説明すると基本給や賞与の待遇について正社員と有期労働者との差をつけてはいけないという事。
これに関しては全く同じ仕事内容であれば分かり易いですが、2人の社員が100%同じ仕事をしているといった事は中々あり得ませんよね。
例えば以下の2人ならどうでしょう。
- 社員A:正社員で、賞与有(全国各地への異動有)
- 社員B:非正規社員(有期)で、賞与無し(異動は無い)
仮に社員AとBが全く同じ内容の仕事をしていたとしても異動の有無の差はありますよね。そうすると果たして不合理と言えるでしょうか?難しいですよね。
では社員Aの賞与が1,000万円だとどうでしょう?いくら異動の有無があっても1,000万の差は大き過ぎませんか?すると社員Bにもいくらかの賞与を支給しないと不合理となるかもしれませんね。
極端な例ですが、要は客観的にみて正社員と非正規社員の差が合理的であるかどうかという事です。
- パート等の短時間勤務者
- 派遣社員等の有期労働者
- 定年後の再雇用での有期労働者
一般的には上記のような方が該当します。
また、正社員との違いは以下の様な部分で判断しましょう。
- 職務の範囲
- 責任の度合い
- 異動の有無
- 配置転換の可能性
賃金だけを一例とすると、ヨーロッパ等では正社員の仕事を100%ととした時、有期労働者の仕事が80%であれば80%分の賃金を支払うといったように差が比例的であるべきとされ、比例的に均衡しています。
一方で日本では弾力的な均衡といって比例的に差をつけなくてもいいが、正社員の仕事が100%で有期労働者の仕事が80%であれば、上記の様な職務の範囲や責任の度合い等も加味しつつ、合理的な範囲で正社員のと有期労働者に差がありすぎないようにするといった少々分かりにくい内容になっています。
働き方改革関連法:③有休の時季指定
これに関しては既に2019年4月より施行されているので既に取り組まれている事だと思います。
また、この年次有給休暇についても労基法第39条で明記されています。
- 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用:労働基準法第39条の1より
また、有休の付与日数についても下記のように労基法第39条の2で明記されています。
| 入社6ヶ月 | 10日の有休付与 |
|---|---|
| 入社1年6ヶ月 | 11日の有休付与 |
| 入社2年6ヶ月 | 12日の有休付与 |
| 入社3年6ヶ月 | 14日の有休付与 |
| 入社4年6ヶ月 | 16日の有休付与 |
| 入社5年6ヶ月 | 18日の有休付与 |
| 入社6年6ヶ月 | 20日の有休付与 |
おそらく皆さんの会社にも就業規則等に明記されているんじゃないでしょうか。
そしてよく勘違いされているのがこの有休の権利は労働者が与えられた権利であり、原則として労働者が時期を指定して申請した際は使用者はその日に有休を与えなくてはなりません。
また、有休の利用目的を聞くのもNGです。自分の有休をどう使おうが会社が知る必要は無く、教える必要もありません。
会社の有休申請用紙に申請理由を記入する欄があるのであれば問題ありです。(空白でも申請できるのであれば問題無し)
ただ、「原則」としたのは理由があり、使用者にも労基法第39条の4で「時季変更権」という労働者の有休申請に対して時期を変更させる権利があります。
有休申請の時季変更権
以下労基法第39条の5。
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
引用:労働基準法第39条の4より引用
この時季変更権で労働者の有給申請の時季を変更させる事が出来るんです。
ただし!「事業の正常な運営を妨げる場合に」とある様に、その労働者が有休を取得する事でお店や部署といった単位ではなく”事業”すなわち会社の運営を左右する程の理由が無いとこの時季変更権は使えないという事です。
社員が1人休む事で会社の運営が左右されるなんて事まず有り得ませんよね。
そしてこの年休制度に2019年4月より義務付けされたのが、使用者に対して企業の大小に関係なく「年次有給休暇が10日以上ある者に対して1年間に5日以上の有休を取得させなければならない」という事。
取得させなければならない5日間は自由に取得させる事も出来ますし、労働者の意見を聴取した上でその希望に沿う様に時季を指定する事も出来ます。
年に5日間を取得している労働者に対しては取得時季を指定する事はできません。
さいごに
以上、働き方改革関連法の中でも私が重要だと思う3つのポイントを紹介させていただきました。
そもそも36協定なんてものが無ければ残業させる事が出来ない訳で、36協定が出来たのも昔は労働組合の普及率が高く、ここまでの長時間労働を誘発するとは思ってもいなかったはずです。
それが今となっては会社が「残業させる為の手段」に変わってしまったんですね。
昔と今とでは時代が違います。知らず知らずの内に会社のいい様に扱われてしまわない様、こういった条文も日々見直しや追加がされていますので労働者もチェックする必要があります。
それでは最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。